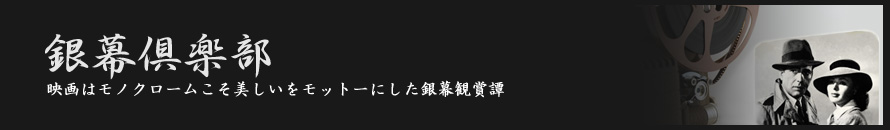栄えある第一回目の銀幕倶楽部の作品に選んだのはキャロル・リード監督の不朽の名作『第三の男』。
実はたまたま先月、ウィーンに行く機会があったので予習のために見直してみたばかりである。実際に撮影の舞台となったウィーンの街を映画のシーンを思い浮かべながら歩いたため、現在この1949年制作の何度も繰り返し見てきた作品が個人的に最も新鮮な映画作品でもある。
また、この映画の全編に奏でられるアントン・カラスのツィターの調べは、日本ではビール会社のCMに使われたばっかりに恵比寿駅の発車音楽にまで使われるほどスタンダード化してしまったので、映画を見たことが無い人でもこの曲を知らない人はいないだろう。
原作はグレアム・グリーン。ただし元々が映画化を前提にストーリーが書かれたものである。戦後の4カ国共同管理化のウィーンを舞台に、はびこる闇商人の陰謀にアメリカの作家が巻き込まれていくサスペンスなのだが、有名になりすぎた映画音楽だけでなく1949年のカンヌ映画祭のパルムドール、1950年度のアカデミー賞撮影賞を受賞したモノクロームの特殊効果を存分に発揮し、映画の教科書とも言われる幾多の名場面で映画史上に残る作品である。
特に映画の後半、オーソン・ウェルズのハリー・ライムが窓の明かりで浮かび上がるように登場するシーン。友人のアメリカ人作家マーティンス(ジョセフ・コットン)が後を追うのだが、大きく伸びた影と足音だけで緊迫した追跡シーンを表現する映像テクニックは何度見ても素晴らしい。名優ウェルズの観覧車でのインパクトの残る台詞と人物表現、焦燥感に満ちた地下道の逃亡シーン、一つ一つのショットのエピソードの集積が物語に命を吹き込み、見るものすべてを緊迫した状況に立ち合わせてしまうのだ。
日本での公開は1953年。封切り以来大ヒットとなり日本の映画製作者たちにも衝撃を与えたのだろう。5回立て続けに見たという故植草甚一氏は当時の「映画の友」の中で、これらの名シーンの数々をこんな風に批評している。
“この映画のストーリーをいくら書いたところで『第三の男』をみた印象が生き生きとしてこないのは、映画によって初めてもっとも効果的に表現できるこれらの細部が文章で表現するのが非常に難しいからです”
また後に日本映画を代表する監督になった当事日活の脚本を書いていた若き熊井啓は、赤木圭一郎のアクション映画『霧笛が俺を呼んでいる』に早速プロットをインスパイアさせて一気に書き上げた。
そして、原作にも無かった強烈なラストシーン。
ハリー・ライムの葬儀の後、落ち葉が舞い散る墓地の並木道。友であるハリー・ライムを裏切ることで窮地を救おうとした愛する女性を待つ男。並木道の彼方から歩いてくるその女性は、しかしながら自分の恋人だったライムへの裏切りを許すことは出来ない。男の前を無言で一瞥することも無く歩き去る女性。
この長い長いシークエンスで男女の心のうちを一言の台詞もなく表現したこのラストによって、『第三の男』は映画史に残る名作となったと言ってもいいだろう。
原作でハッピーエンドに終わらせてしまったグレアム・グリーンは映画を見た後、キャロル・リードに対して“負けてしまったよ”と言わせしめたそうである。
この作品にかかわったほとんどの人がすでに鬼籍に入ってしまった中、この美しく切なくもやりきれないラストシーンを“歩いた”ヒロイン、アンナを演じたアリダ・ヴァリだけがつい最近まで健在だったのだが、一昨年84歳で息を引き取った。

●第三の男
(1949年英ロンドン・フィルム・米セルズニックプロ作品)
原作・脚本/グレアム・グリーン
製作・監督/キャロル・リード
撮影/ロバート・クラスカー
音楽/アントン・カラス
出演/ジョセフ・コットン(ホリー・マーティンス)
アリダ・ヴァリ(アンナ)
トレヴァー・ハワード(キャロウェー大佐)
バーナード・リー(ペイン軍曹)
エルンスト・ドイッツェ(クルツ男爵)
オーソン・ウェルズ(ハリー・ライム)
1949年 カンヌ映画祭パルムドール
1950年 英国アカデミー賞 作品賞
1950年 アカデミー賞 撮影賞(白黒部門)
1953年 キネマ旬報ベストテン2位